
| 書評/新聞記事 検索 図書新聞は、毎週土曜日書店発売、定期購読も承ります |
|

|

|

|
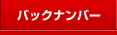
|

|

|
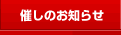
|
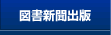
|

|
【重要なお知らせ】お問い合わせフォーム故障中につき、直接メール(koudoku@toshoshimbun.com)かお電話にてバックナンバー・定期購読の御注文をお願い致します。
|
学術
|
|
生物学者の待ち望んでいた生物の界系統研究史序説
|
|
書籍・作品名 : われら古細菌の末裔:微生物から見た生物の進化
著者・制作者名 : 二井一禎,共立出版 (2023)
|
|
岩田隆太郎
68才
男性
https://www.facebook.com/ryutaro.iwata
|
 |
| 宗教的な異存を別にすれば,全生物はダーウィン以来,一本の巨樹の根幹とそれから派生した無数の枝分かれに例えられることは常識となって久しい。それでは,この全生物の進化系統樹の根幹の部分は一体どうなっているのかについてはこれまで推測の域を出ず,ずっと曖昧なままで,何となく分かったようでいて,結局何も分かっていないというのが実情であった。
この書物の著者は,樹木の病原性・寄生性線虫および病原菌の研究者として長年の研究歴を持った方である。しかしここでは,これらの生物(複数の界!)の研究歴をバックボーンとして,何と,上述の全生物の進化史の根幹の部分の解明に迫る最新の研究のとりまとめという,私たち生物学者が待ち望んでいた著作を実現したのである。 私たち世代が約半世紀前に学校で学んだ生物分類は,植物界・動物界の生物二界説であったが,原核生物の合体による真核生物の誕生を中心に据えたホイッタカーの生物五界説(モネラ界(原核生物),原生生物界,菌界,植物界,動物界)は,当時目から鱗の新説であった。その後ウーズとフォックスの1977年の論文を嚆矢とした分子系統解析法の適用により,モネラ界が実は古細菌と(真性)細菌に二分され,しかも最も根源的な二分はこの古細菌とそれ以外の全生物の間にあり,全生物はアーキア(古細菌),バクテリア(細菌),ユーカリア(真核生物)の3ドメインに分けられるとする説が出るに及んで,上述の生物系統樹の根幹部分にぼんやりとした輪郭がようやく見えてきた。さらに「アーキア」(「古」細菌)とはいうものの,むしろ生命の起源はバクテリア(細菌)にあり,そこからアーキアが,さらにそのアーキアからユーカリアが派生したとの説が有力となって,いよいよ本書のタイトルが意味を持って来るに至る。ミトコンドリアの誕生などに見る上述の「合体」は,古細菌に細菌が入り込む形が基本であるとされ,さらにアーキア内部で続々と新タクサが発見され,我々ヒトを含むユーカリアの系統的位置が次第に明らかとなっていく。ということで,本書はいわば生物の界系統研究史序説といえる。今後本書の類書,さらには本格的な関連専門書が続々と著されることが予測されるが,本書は生物学の根幹にあたるこのテーマの解説書としては画期的であり,その意味で歴史的な一冊といえよう. |
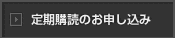
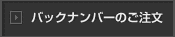
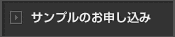
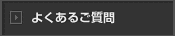
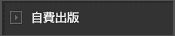
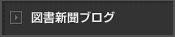
 サイト限定連載 サイト限定連載
|
||
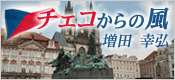
|
||
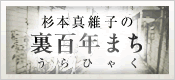
|
||
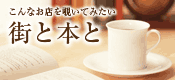
|
||
最新刊 |
||
| 『新宿センチメンタル・ジャーニー』 | ||
| 『山・自然探究――紀行・エッセイ・評論集』 | ||
| 『【新版】クリストとジャンヌ=クロード ライフ=ワークス=プロジェクト』 |
||
| ■東京■東京堂書店様調べ | ||
| マチズモを削り取れ (武田砂鉄) |
||
| 喫茶店で松本隆さんから聞いたこと (山下賢二) |
||
| 古くて素敵なクラシック・レコードたち (村上春樹) |
||
| ■新潟■萬松堂様調べ | ||
| 老いる意味 (森村誠一) |
||
| 老いの福袋 (樋口恵子) |
||
| もうだまされない 新型コロナの大誤解 (西村秀一) |
||
 定期購読
定期購読

 サイト限定連載一覧
サイト限定連載一覧