
| 書評/新聞記事 検索 図書新聞は、毎週土曜日書店発売、定期購読も承ります |
|

|

|

|
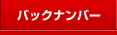
|

|

|
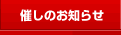
|
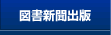
|

|
【重要なお知らせ】お問い合わせフォーム故障中につき、直接メール(koudoku@toshoshimbun.com)かお電話にてバックナンバー・定期購読の御注文をお願い致します。
評者◆増田幸弘
ヤン・ライヒの思い出
No.2943 ・ 2009年11月28日

チェコを代表する写真家ヤン・ライヒが2009年11月14日に亡くなった。
ライヒにはじめて会ったのは1992年のことだった。パルコ出版から出すプラハをテーマにした本に、彼の写真を載せるためである。ライヒはプラハ城の裏手にあるノヴィー・スヴィエット(新世界)通りという、不思議な雰囲気が漂う家に住んでいた。そのとき彼はまだほとんど無名の写真家だった。そんな彼のもとを写真を見せて欲しいという日本の編集者が訪ねてくるなんて、きっと驚きだったにちがいない。
1989年に共産体制が崩壊してまだまもなく、みなが希望を持っていた。少なくともぼくにはそう感じられた。ライヒはこんなことを言っていた。
「撮影した写真を絵はがきにして売る。そんなこと、どうでもいいと思うかもしれないけれども、いまのぼくにとって、こんなにうれしいことはないんだ。共産体制のときはそんなことさえできなかったのだから。いまは、自由にできる」
ライヒのいう「自由」という言葉をそのときは軽く聞き流していたが、そのとき以来、その意味を何度も繰り返し考えてきた。
ライヒはヤン・スデックの直系の弟子だった。スデックが使っていた大型写真機を受け継いで使っている、と彼は言っていた。たしかにライヒの写真にはスデックと共通するものがある。しかし、ライヒの写真にはライヒならではのものがあるとそのとき感じた。
それからライヒは1冊1冊、確実に写真集を出版していった。プラハの風景だった。共産体制のときに撮ったものが多かった。ライヒは共産体制のときもフリーランスだった。しかし、それは許されないことでもあった。フィルムの入手にも、印画紙の入手にも、彼は苦労した。1年に数カットしか撮れなかった年もあると聞いた。
ライヒは途中から、出版社から写真集を出すのをやめてしまう。その代わり、奥さんのヤナが出版社Galerie Novy Svetを立ち上げ、そこから刊行することにした。出版社で出していては、出版社の意向に従わなくてはいけないことが多く、制約があると感じていたからだという。
こうして出版したのが「ボヘミア」と題された写真集だった。印刷技術も、紙質もこだわり抜いたこともあって、2005年に刊行されたこの本は、チェコで1年のうちに出版されたなかでもいちばん美しい本に送られるという「Magnesia Litera Book Award」を受賞した。
日本の出版状況がおかしくなり、いったいどうなっていくのだろう、これからどうすればよいのだろうと考えたとき、真っ先に思い出したのがライヒのことだった。ライヒのありようは出版の本来あるべき姿を示しているように感じた。ぼくが2006年からプラハに住みはじめたのはそのためだった。
久方ぶりに新世界通りのライヒの家を訪ねたとき、彼は「何年ぶりだっけ?」と問いかけてきた。そして、お互いが過ごした日々のことを淡々と話した。それからというもの、ときどき彼のもとを訪ねては、あれこれ話すようになった。
2007年には念願だった東京での展覧会を実現することになった。チェコセンターと、Place Mという瀬戸正人が主催する写真ギャラリーで写真展を開き、それに合わせてライヒ夫妻もはじめて来日することになった。ぼくもその来日に合わせ、プラハから東京を訪ねた。この年、写真集「A House in the Country」がGalerie Novy Svetから出版された。大型カメラで撮影された写真のほか、ライカで撮った家族のスナップ写真もページを飾った。
さらに2008年にはチェコ国立美術館のトリエンナーレの学芸員の一人となったぼくはライヒのことを招いた。美術館の館長は写真をまったく認めないことで知られていることもあって、ライヒは最初渋った。それでもせっかくの機会ということもあって、「A House in the Country」から選んだライヒの写真6点が国立美術館に展示されることになったことは、ぼくにとっては大きな喜びとなった。チェコの学芸員ではなく、日本の学芸員が彼の写真を選んだこともおもしろい。
写真家といっても、ぼくがやっているように新聞や雑誌の写真を撮るわけではなかった。ただひたすら、自分のためだけに写真を撮ってきた。だれかに見て欲しいとか、だれかに認められたいとか、そうした人間であればだれでももっているような欲をライヒに感じたことをぼくは一度もない。その意味でライヒの写真への姿勢は徹底してアマチュアであり、そして徹底してプロフェッショナルだった。
会うたびにライヒはいつもユーモアを交えて語りかけてきた。いつも笑いがあった。なにごとにも謙虚だった。それはチェコ人には珍しいことだった。新世界通りにあるライヒのアトリエを訪ね、ブザーを押すと、ライヒは上から窓から顔を出し、手を振った。そして、大きな黒い犬といっしょに下まで階段を降りてきて、扉を開けてくれた。
あの家を訪ねてももうライヒがいないと考えると、さみしくて仕方がない。彼はぼくにとって、チェコの父のような存在だったのである。
ライヒにはじめて会ったのは1992年のことだった。パルコ出版から出すプラハをテーマにした本に、彼の写真を載せるためである。ライヒはプラハ城の裏手にあるノヴィー・スヴィエット(新世界)通りという、不思議な雰囲気が漂う家に住んでいた。そのとき彼はまだほとんど無名の写真家だった。そんな彼のもとを写真を見せて欲しいという日本の編集者が訪ねてくるなんて、きっと驚きだったにちがいない。
1989年に共産体制が崩壊してまだまもなく、みなが希望を持っていた。少なくともぼくにはそう感じられた。ライヒはこんなことを言っていた。
「撮影した写真を絵はがきにして売る。そんなこと、どうでもいいと思うかもしれないけれども、いまのぼくにとって、こんなにうれしいことはないんだ。共産体制のときはそんなことさえできなかったのだから。いまは、自由にできる」
ライヒのいう「自由」という言葉をそのときは軽く聞き流していたが、そのとき以来、その意味を何度も繰り返し考えてきた。
ライヒはヤン・スデックの直系の弟子だった。スデックが使っていた大型写真機を受け継いで使っている、と彼は言っていた。たしかにライヒの写真にはスデックと共通するものがある。しかし、ライヒの写真にはライヒならではのものがあるとそのとき感じた。
それからライヒは1冊1冊、確実に写真集を出版していった。プラハの風景だった。共産体制のときに撮ったものが多かった。ライヒは共産体制のときもフリーランスだった。しかし、それは許されないことでもあった。フィルムの入手にも、印画紙の入手にも、彼は苦労した。1年に数カットしか撮れなかった年もあると聞いた。
ライヒは途中から、出版社から写真集を出すのをやめてしまう。その代わり、奥さんのヤナが出版社Galerie Novy Svetを立ち上げ、そこから刊行することにした。出版社で出していては、出版社の意向に従わなくてはいけないことが多く、制約があると感じていたからだという。
こうして出版したのが「ボヘミア」と題された写真集だった。印刷技術も、紙質もこだわり抜いたこともあって、2005年に刊行されたこの本は、チェコで1年のうちに出版されたなかでもいちばん美しい本に送られるという「Magnesia Litera Book Award」を受賞した。
日本の出版状況がおかしくなり、いったいどうなっていくのだろう、これからどうすればよいのだろうと考えたとき、真っ先に思い出したのがライヒのことだった。ライヒのありようは出版の本来あるべき姿を示しているように感じた。ぼくが2006年からプラハに住みはじめたのはそのためだった。
久方ぶりに新世界通りのライヒの家を訪ねたとき、彼は「何年ぶりだっけ?」と問いかけてきた。そして、お互いが過ごした日々のことを淡々と話した。それからというもの、ときどき彼のもとを訪ねては、あれこれ話すようになった。
2007年には念願だった東京での展覧会を実現することになった。チェコセンターと、Place Mという瀬戸正人が主催する写真ギャラリーで写真展を開き、それに合わせてライヒ夫妻もはじめて来日することになった。ぼくもその来日に合わせ、プラハから東京を訪ねた。この年、写真集「A House in the Country」がGalerie Novy Svetから出版された。大型カメラで撮影された写真のほか、ライカで撮った家族のスナップ写真もページを飾った。
さらに2008年にはチェコ国立美術館のトリエンナーレの学芸員の一人となったぼくはライヒのことを招いた。美術館の館長は写真をまったく認めないことで知られていることもあって、ライヒは最初渋った。それでもせっかくの機会ということもあって、「A House in the Country」から選んだライヒの写真6点が国立美術館に展示されることになったことは、ぼくにとっては大きな喜びとなった。チェコの学芸員ではなく、日本の学芸員が彼の写真を選んだこともおもしろい。
写真家といっても、ぼくがやっているように新聞や雑誌の写真を撮るわけではなかった。ただひたすら、自分のためだけに写真を撮ってきた。だれかに見て欲しいとか、だれかに認められたいとか、そうした人間であればだれでももっているような欲をライヒに感じたことをぼくは一度もない。その意味でライヒの写真への姿勢は徹底してアマチュアであり、そして徹底してプロフェッショナルだった。
会うたびにライヒはいつもユーモアを交えて語りかけてきた。いつも笑いがあった。なにごとにも謙虚だった。それはチェコ人には珍しいことだった。新世界通りにあるライヒのアトリエを訪ね、ブザーを押すと、ライヒは上から窓から顔を出し、手を振った。そして、大きな黒い犬といっしょに下まで階段を降りてきて、扉を開けてくれた。
あの家を訪ねてももうライヒがいないと考えると、さみしくて仕方がない。彼はぼくにとって、チェコの父のような存在だったのである。
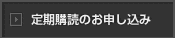
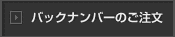
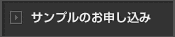
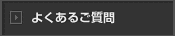
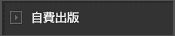
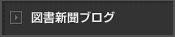
 リンクサイト リンクサイト
|
||

|
||

|
||

|
||

|
||
 サイト限定連載 サイト限定連載
|
||
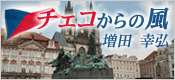
|
||
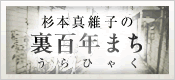
|
||
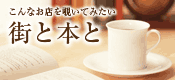
|
||
最新刊 |
||
| 『新宿センチメンタル・ジャーニー』 | ||
| 『山・自然探究――紀行・エッセイ・評論集』 | ||
| 『【新版】クリストとジャンヌ=クロード ライフ=ワークス=プロジェクト』 |
||
| ■東京■東京堂書店様調べ | ||
| マチズモを削り取れ (武田砂鉄) |
||
| 喫茶店で松本隆さんから聞いたこと (山下賢二) |
||
| 古くて素敵なクラシック・レコードたち (村上春樹) |
||
| ■新潟■萬松堂様調べ | ||
| 老いる意味 (森村誠一) |
||
| 老いの福袋 (樋口恵子) |
||
| もうだまされない 新型コロナの大誤解 (西村秀一) |
||
 定期購読
定期購読

 サイト限定連載一覧
サイト限定連載一覧